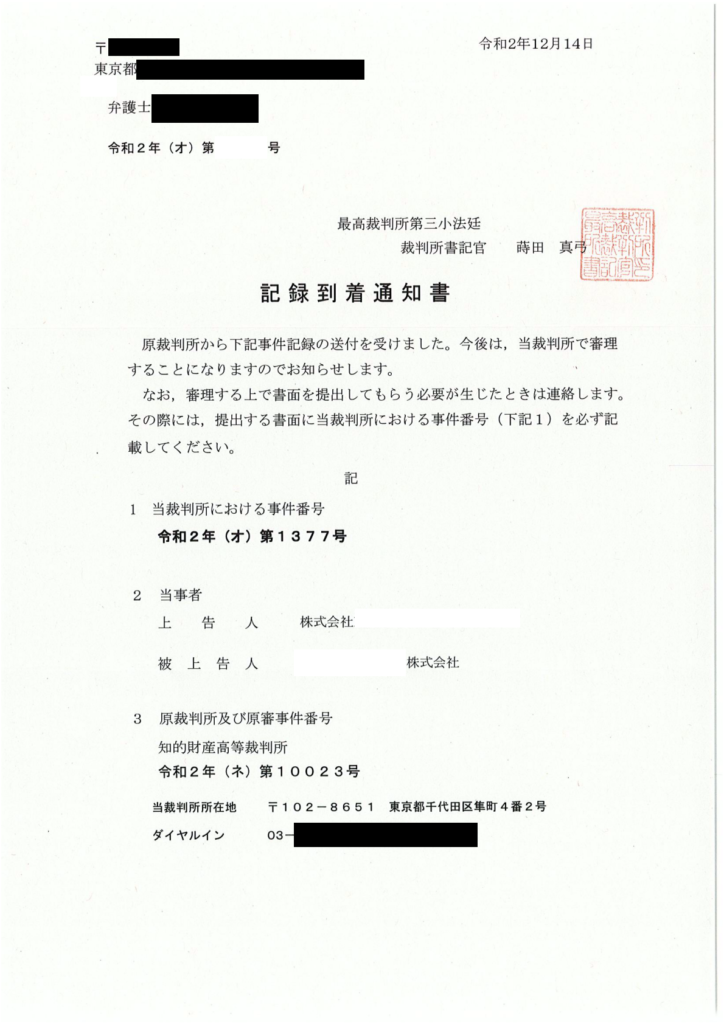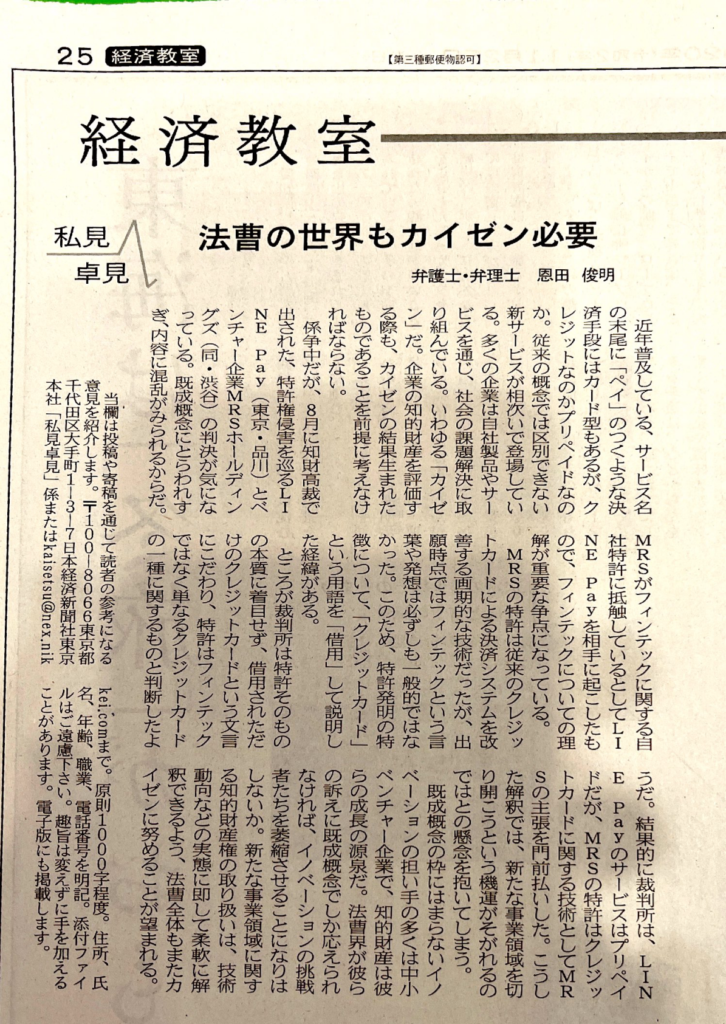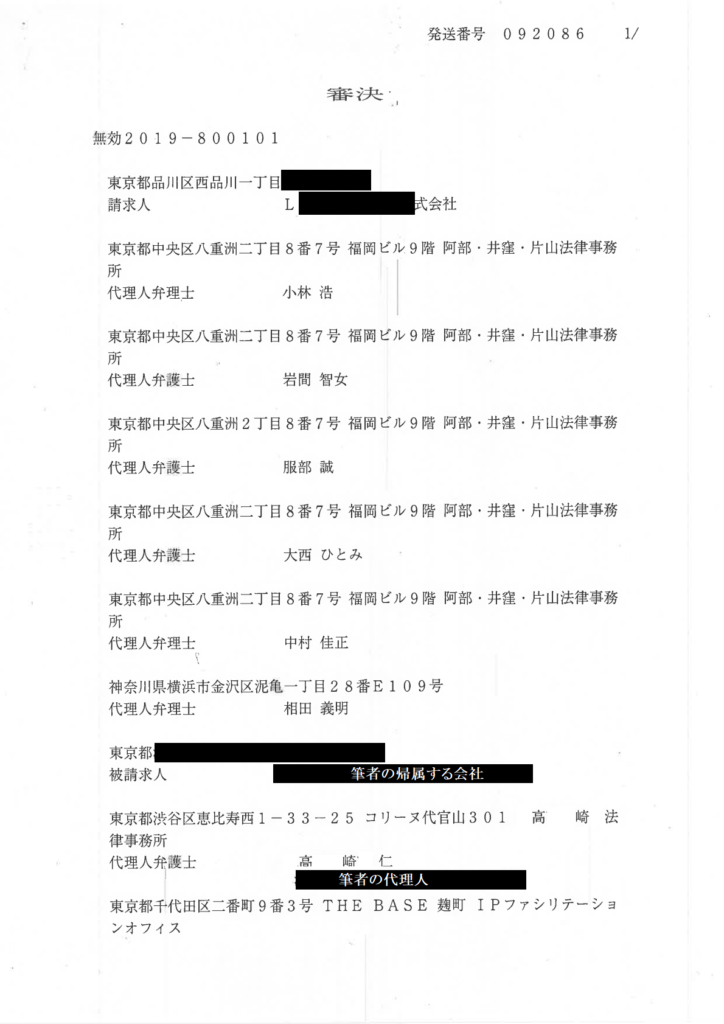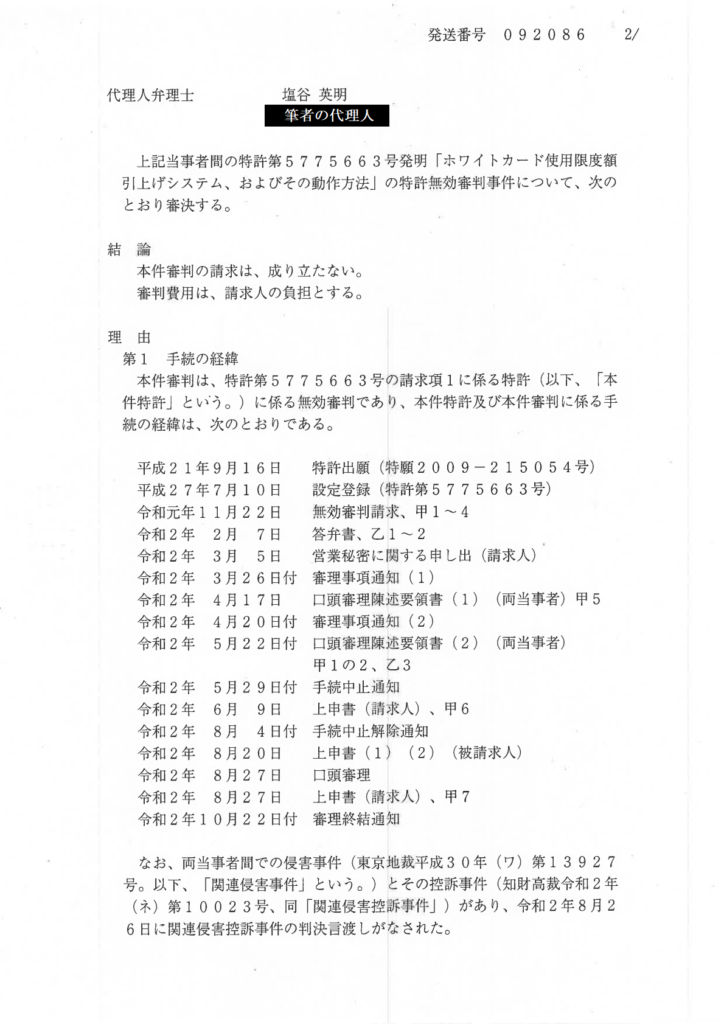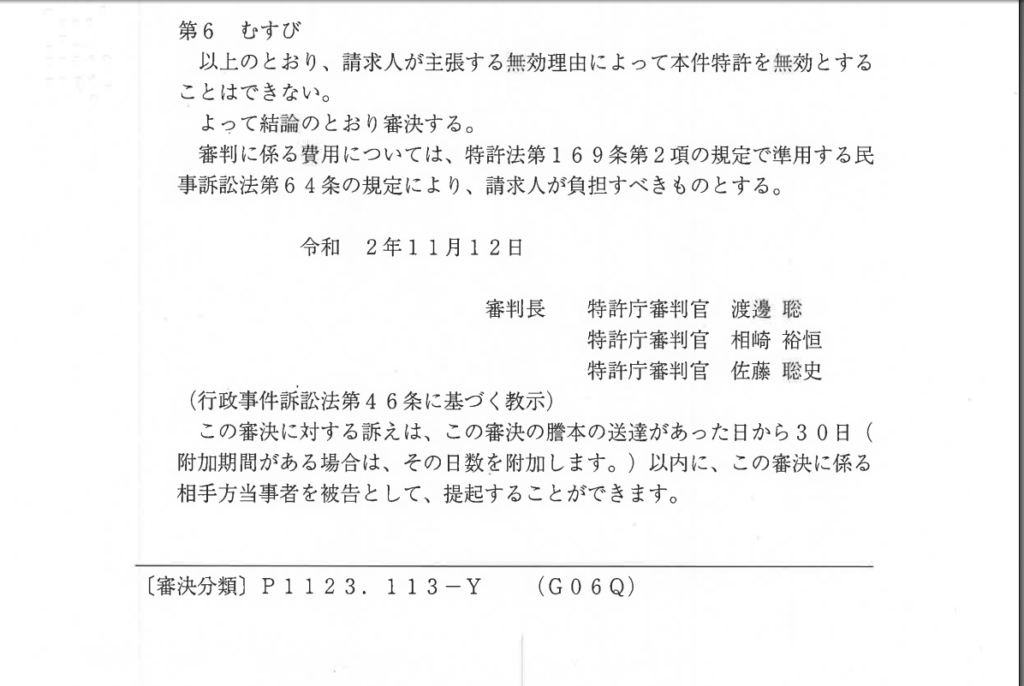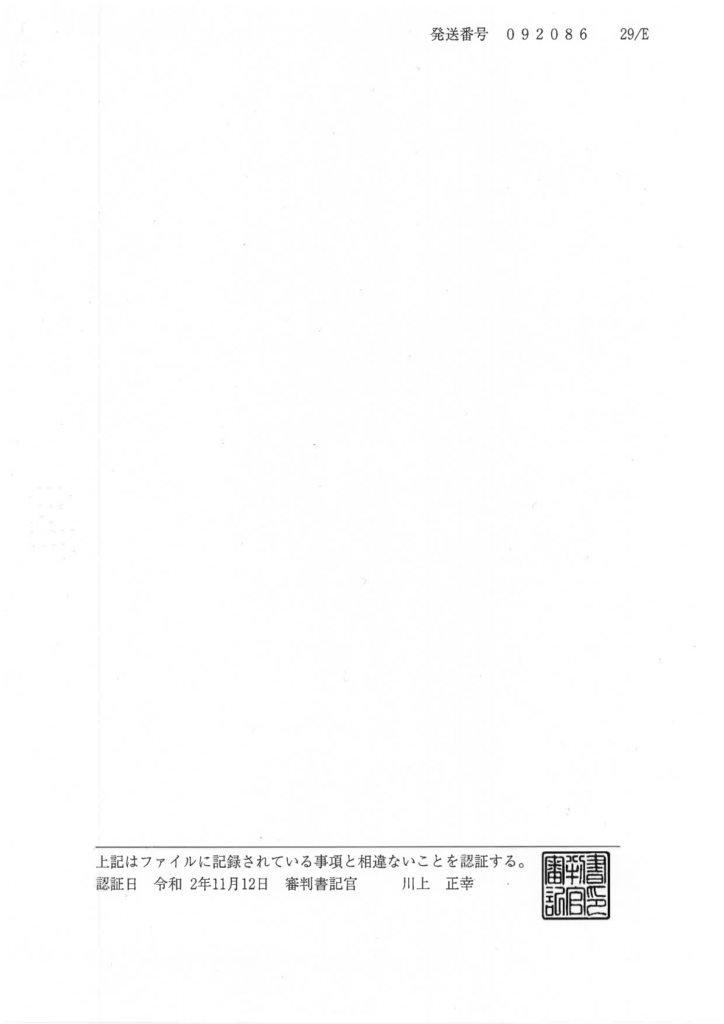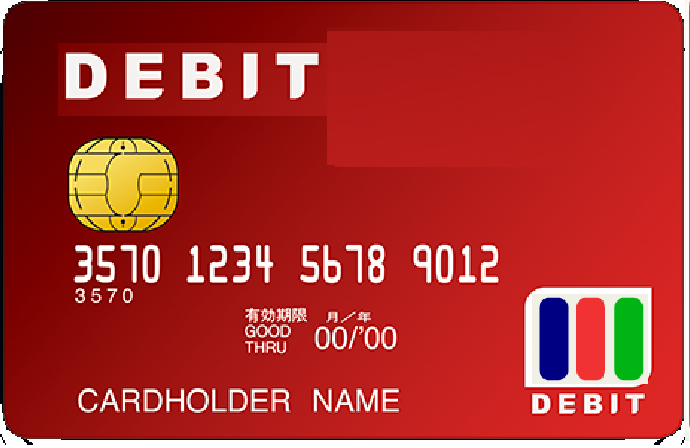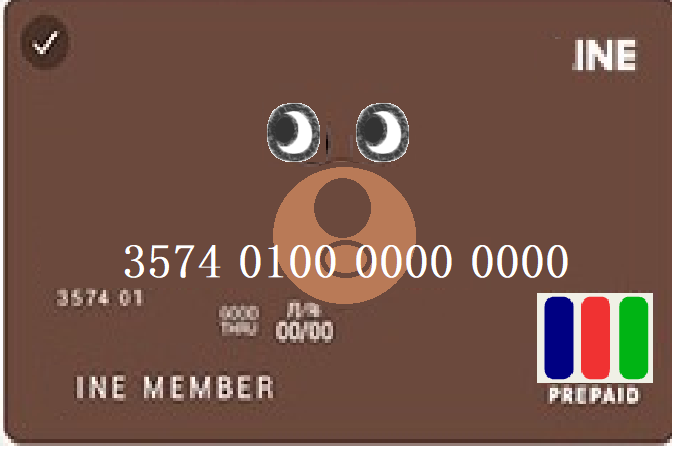本来NFTとはNon-Fungible Tokenの略語であり日本語に直訳すると「非代替性のしるし」と言う言葉となります。さてそれでは筆者kozykozyが発明したSssNFT(トリプルエスエヌエフティ―或いはスリーエスエヌエフティー)とは何なのでしょうか?
SssNFTの最初のSはsafety(安心)、次のsはsecure(安全)、最後のsはstable(安定)と言う意図以て生み出した造語です。その後に続くNFTなので「安心で安全で安定した非代替性のしるし」と言うのが直訳した意味となります。
さっぱりわからん・・と、知り合いから言われてしまいました。実はSssNFTの発明を正確に表現すると非代替性トークンの発明では無く、「安心して安全に安定した非代替性トークンを用いた取引を可能とするプラットフォーム」の発明と言うのが正しい表現となります。もう少しに正確に表現しますと「SssNFT」は筆者kozykozyが従前に発明した「イーマイ(E-mi)のような特徴をもったブロックチェーンを基盤とした安心して安全に安定した非代替性取引が実行されるプラットフォーム」となります。
NFT取引は思った以上に事故が多い
非代替性トークン(NFT)が生成される時、その情報がオリジナル情報である事が必須となります。が、しかし、画伯kozykozyが「この絵は僕が書いたオリジナルの絵だ!」と主張してNFT化したとして、その後そのNFTを第三者に公開したり、譲渡したり、譲受人から対価を受領したり・・と様々な取引が将来生ずるわけなのですが、例えば譲り渡して対価を受領した後そのプラットフォームから脱退し、譲受人が絵画の原作者が実は全く別人物で有った事を知った場合、そのNFTは全く無意味なものとなる。実際世の中ではNFT取引に於いてこの様な事故は数多く発生しており、非代替性トークンによって真贋が必ずしも証明されていないのが事実で、多額なNFT取引が全くもって偽りの取引であったりする事象が日本でも見受けられる事から、金融庁がNFT取引業に従事する者には非常に厳しい法的な規制を掛けている事からもその危険性が伺える。
そもそもNFTのが指し示す「現実有体無体物」って本物かどうか特定できるの?
そもそもNFT化する「現実有体無体物」が本物かどうかを予め特定する事は事実上不可能である。譲渡・譲受取引後、対価取引が行われた後、ある一定の時間が経過後、そのNFTが指し示す「現実有体無体物」の真の所有者が表れて、当該プラットフォーム上の取引事実を否定すると、その取引記録はブロックチェーン上から消失する事は無くても、取引自体は全く無意味となる。しかしそのNFTデータを生成した者(NFTデータの生成をマーケットのとある人物から依頼を受けてブロックの生成が成された場合、この表現は正確な表現では無いが)は既に当該プラットフォームからは脱退しており、その不正取引者を追跡して取り締まる事も不可能なのである。
SssNFTが定義する非代替性トークンのSafety(安心)secure(安全)stable(安定)とは
SssNFTプラットフォームでは「現実有体無体物」を、マーケットからブロックチェーン上に提出する者(譲り渡し人)も、その現実有体無体物を受けてNFTを生成しブロックチェーンに記録する者(マイニング者)も、マーケットで購入する者(譲り受け人)などNFT取引に該当する全ての参加者のリアリティな世界での個人属性情報を把握しており、属性情報を把握しいる状態に応じて、取引に参加できる行為が異なってくるのである。
頼深度と言う新発明!
取引参加者の各々の属性情報にはピンからキリまで様々な情報が有るが、取得したそれらの属性情報のクオリティに応じて信頼の度合いに尺度を数値化しブロックチェーン上で行える行為に制限を掛けていく、正確に言うと頼深度ゼロの時はSssNFT上ではあらゆる取引が不可能な状態であり、その状態を「頼深度ゼロ」と定める。
属性情報の取得数が増えて、且つ正確に当人を特定できる性格な情報で有る場合「頼深度」の深度の数値が加算されていき、取引における行為も拡大していく。
又対価の支払い手段として仮想通貨を排除しいるのでトークンは仮想通貨の授受を示さず、法定通貨の取引を指し示す事となる。この法定通貨をブロックチェーンの世界から銀行のネットワーク群へ出力する時に、この頼深度は重要な指数となる。所謂仮想の世界からリアリティな世界のIN/OUTは非常に不安定で希薄なゲートウェイを2度通過する事となるので、頼深度はリアリティな世界での通行手形して有効であり、リアリティ世界でもバーチャル世界でも共通の通行手形として使える「頼深度」はこれまでのブロックチェーンやNFTプラットフォームには全く存在しなかった概念である。
投資型性質のブロックチェーンから真の分散化台帳システムへの成長
これまでブロックチェーンの特徴であった仮想通貨と匿名性とオープン型と言う性質は仮想通貨を投資対象として成長してきたが、それ故にNFTの取引も従前の仮想通貨に期待されてきた範囲を脱する事が無く、期待値以上の成長に至っていない。
又、従来のNFT取引を中心に日本国内では銀行群などが新為替プラットフォームにチャレンジしているものの、NFT格納の為のブロックの取得値が乱高下する為銀行為替のプラットフォームしては不向きである。投資型性質のブロックチェーンから新の分散型台帳システムへ成長して生まれ変わる必要がある。
SssNFTは世界で初めてのコンソーシアム型の属性特定取引法定通貨分散化台帳システム型プラットフォームである。
前述してきた内容を実現する為にSssNFTでは個人の属性情報を開示する事のみで参加を許可し、ブロックの生成もサーバーによるオートカルクでは無く手動ナンス採掘方式を前提に、全ての対価取引は法定通貨を実現し、テスト運用を行ってきた。
2年間の実証実験によりこのSssNFTは安心・安全・安定した分散型台帳システムで有る事が証明され、マイニング参加者も、NFTデータの生成依頼者も、データ譲受者も全ての属性情報に頼深度が設定されおりSssNFTの仕組みが美しく調和されて稼働している。
言葉を選ばずに言うと、ブロックチェーンの「功罪」の「罪」の部分にメスを入れ、それらのブロックチェーンの「罪」の箇所を徹底的に排除し生みなおしした全く新しNFTプラットフォームである。
最後に・・・
従来のブロックチェーンにおけるNFTデータは高額な値が付く事だけを期待して運用されており、それらの思想が分散化台帳システムとしてNFT化を期待したい様々なものが、その高額なコストに耐えられず実用化の検討にも至らずどんどんとNFT化の未来から遠ざかっている。
SssNFTは、本来の分散化台帳システムとしての動作を基本とし取引の対価を法定通貨のみとして相場的要因の乱高下を排している。それゆえNFT化されるデータの実用化の裾野が広くなり、ギャランティカード、契約書、楽譜、作詞譜、財産目録所、遺言書、著作権、特許権、初案権、レシピ・・・様々なものがNFT化できる。
簡単な仕組みに感じるが、匿名性と仮想通貨を基軸として成長してきたブロックチェーンの世界では実現できなくなってしまった非匿名性と法定通貨取引を基軸として、頼深度数理によってそのNFT取引の行為に制限を掛かる(自分以外のプラットフォームの意志により行為のせいっ減が掛かる)この仕組みはここに書き連ねた言葉以上に革命的な意味を有している。